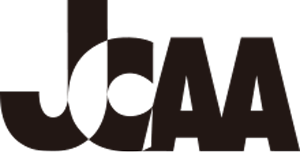宣言
宣言
編曲著作権に関する宣言
-
一つの楽曲が CD 等の形で世に出るまでに、編曲家による楽曲のアレンジを経ているのが一般である。このアレンジによって、その曲は次元の高い楽曲へと昇華され、一つの商品として完成される。CD 等の制作においてしめる編曲家の役割は極めて重要なものであり、編曲家は作詞家、作曲家、演奏家、制作者等と共にわが国の音楽文化の基礎を支える柱の一つである。
聞き手やカラオケ愛好家の多様な嗜好に対応するために、今日、編曲家の役割は日増しにその重要性を増している。
しかし、このような編曲家の重要な役割にもかかわらず、現在の音楽産業界においては、編曲家の音楽文化への貢献と基本的な権利(著作権)について、正当な評価がなされておらず、著作権法上の権利は全くの「画餅」の状態にある。
世上、編曲家の著作権を形式的には認めつつも、「音楽業界の商慣習として編曲家への配分は認められない」とし、実質的に編曲家の著作権を否定する見解があるが、当会はカラオケが今日のように隆盛をきわめ、デジタル方式の通信カラオケが瞬時に店舗に供給され、編曲家の業績が連日無償で使用しつづけられている現状に照らして、上記の見解は到底妥当性をもたないものと考える。マルチ・メディア時代を迎え、多くの音楽ソフトが一般家庭に配信されようとしている現在、編曲家の業績の無償使用を放任することは、公平の大原則に著しく背馳するものである。
編曲家をめぐるこのような現状に鑑み、当会は、わが国における編曲家の集団の文化的責務として、編曲著作権に関する以下の宣言をなすものである。
- 編曲著作権は編曲がなされたその時に成立し、当会所属の会員は、文書による明示の公正な合意による場合を除いて、編曲著作権を第三者に譲渡しない。
- 楽曲が最初に公表されたときの編曲(イニシャル・アレンジ)を使用する場合、これを使用する関係者は、そのイニシャル・アレンジをした編曲家の著作権(録音権・演奏権等の著作財産権)を尊重し、適正な使用料をその編曲家に支払うべきことを求める。
- 編曲家は自らの編曲著作物について著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)を有するものであり、編曲著作物を使用する場合、その関係者は氏名表示等を公正に履践し、著作権法を遵守されるよう求める。
1995年9月1日
日本作編曲家協会(JCAA)
会長 服部克久
※役職は宣言発表当時のもの
作編曲家の氏名表示に関する宣言
-
今日、音楽は、テレビ、ラジオ、有線放送、インターネット、CD、ゲーム、カラオケ、映画、舞台音楽等の多くの領域で使用されているが、使用楽曲の作曲者、公表時編曲者の氏名表示がなされていないものが多々見受けられる。
この現状に鑑み、当会は著作権法19条に基づき、私的利用の範囲を超えて楽曲を使用する全ての場合において、作曲者並びに公表時編曲者の氏名表示を履践されるよう、音楽制作者、放送事業者、有線放送事業者、インターネットサーバーとホームページ保有者、テレビゲーム制作者、カラオケ制作者、映画製作者、舞台音楽制作者、その他一切の音楽制作関連事業者各位に対し、会員の総意によって宣言するものである。
2004年6月28日
日本作編曲家協会総会決議
『スタジオ・アテンド料』実施に関するお願い
-
平素より、私ども日本作編曲家協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
当会では1995年より、録音現場におけるアレンジャーの長時間立ち会いが、編曲料や指揮料だけでは十分に補償されない実情を踏まえ、別途費目として「スタジオ・アテンド料(立会い料)」を設定し制作関係各位にご請求申し上げることについて、ご理解とご協力をお願いしてまいりました。具体的には、以下の内容です。
録音開始の最初のセッションは、通常ベイシックなリズムセクションの録音をおこなうことに使われていますが、この部分についての報酬はこれまでの「指揮料」として受けさせて頂き、この最初のセッションを超えた部分(ふつう、弦・管・シンセ・コーラス等のダビングやトラックダウンの時間帯となります)について、「スタジオ・アテンド料」を申し受けさせて頂きます。
1995年以降、30年の間に制作環境は大きく変化し、DAWを中心としたソフト音源やシンセサイザーによるサウンド構築、録音後のボーカル編集、追加ダビング、リモートセッションやオンラインレビューなど、アレンジャーが音楽制作において果たす役割は多様化するとともに一層拡大しております。現代のアレンジャーは単なるスコア提供者ではなく、サウンドデザイン、演奏ディレクション、全体バランスの監修など、作品の完成度を左右するスーパーバイザーとしての責務を担っています。
従来型のスタジオ録音においても、初回のベーシックセッションだけでなく、弦・管・シンセ・コーラス等のダビングやボーカル録音、トラックダウンの確認等に長時間立ち会い、必要に応じて即時対応することが制作現場では不可欠になっております。しかしながら、こうした編曲以外の労力が十分に評価されず、実質的にアレンジャーが無償に近い形で作業を負担するケースが散見されます。つきましては、1995年の導入当初からの趣旨を踏まえつつ、現代の制作環境に即した形での「スタジオ・アテンド料」として、制作関係各位にご請求申し上げることについて改めてご理解賜りたく存じます。
なお、「指揮料」と「スタジオ・アテンド料」の金額については、個々のアレンジャーによって個人差のあるところですが、時間あたりの「スタジオ・アテンド料」の金額は、「指揮料」より低額を基本としつつ柔軟に調整いたします。
私たちは、より良い音楽を届けるために常に創意工夫と研究を重ね、制作現場での最良の判断を提供することを使命としています。そのためにも、アレンジャーの時間と労力に対する適正な評価が不可欠です。
制作現場における円滑な進行と、作品クオリティのさらなる向上のため、本制度の趣旨をご理解のうえ、今後とも「スタジオ・アテンド料」の実施にご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。